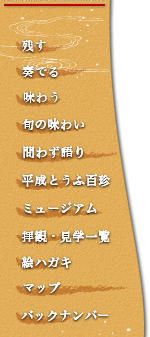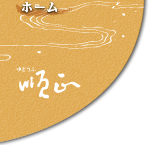和風建築に洋風の手法を取り込んだ造りの建物。京都市指定有形文化財に指定されています。
2013年大河ドラマ「八重の桜」の主人公・八重は、維新後、兄を頼って京都へ移り住みます。そしてほどなく、キリスト教主義の私立学校設立を志していた新島襄と出会い、再婚。彼らが暮らした住居が、京都御苑のすぐ東に残されています。現在、一階と附属家が公開されており、多い日で500人もの見学者が訪れているそうです。
公家の高松保実(やすざね)より屋敷の半分を新島襄が賃借し、同志社大学の前身である同志社英学校を開校したのは1875年(明治八年)。「当時はまだ、教師二人、生徒八人という規模でした」と話すのは、同志社社史資料センター・社史資料調査員の布施智子さん。英学校は翌年、旧薩摩藩邸跡地へ移転。その後、襄は高松邸を購入、自宅を建築したのでした。
襄や同校の教師・W・テイラーの助言を受けて建てられた邸宅は、和風建築にコロニアル様式を取り入れた斬新なスタイル。三方向にバルコニーがあり、東のバルコニーからは大文字山がよく見えたそうです。
床を高くして庇を深くするなど夏の暑さを和らげる工夫を施し、当時としては画期的なセントラルヒーティングも設置。フローリングの部屋には椅子やテーブルが並び、応接室には八重が愛用したと言われるオルガンが残ります。キッチンは土間のない現代風で、まだ珍しかった洋式のトイレもありました。しかし、全てが洋風なのではなく、障子欄間や襖、箱階段など、和の手法も活かされているのが特徴的です。
「書斎も当時のまま残っています。壁一面が書棚になっていて、その八割は洋書。学生は、彼の書斎をまるで図書室のように利用していたそうですよ」と布施さん。約18畳の応接間は、教室や職員室、会議室としても使用。学校運営に力を尽くす夫妻の姿が偲ばれます。
洋風の生活を送っていた八重ですが、襄の死後、一階を改造して茶室を設置。晩年は、和の生活へ回帰した部分もあったようです。以降、彼女は永眠するまでこの場所に住みますが、自宅の土地建物は、1907年(明治40年)に同志社へ寄付されていました。
「校務や伝導で東奔西走する襄と、彼を支えた八重。夫妻が暮らした私邸から二人が実践した洋風の生活や、人々との交流など、家庭での二人の姿を垣間見ることができるのではないでしょうか」。 |
|

「旧邸では、襄と八重の在世中の様子を想像できるように保存しています。建物だけでなく、洋家具からも、当時としては新しい彼らの洋風の暮らしぶりが感じられます」。
|