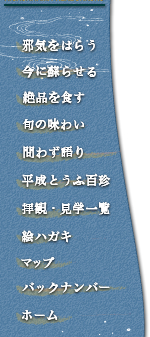美しいほどに使い込まれた彫刻刀。その柄と刃は、永年大切に使われていることがうかがえる優しい光沢を放っています。
顔見世を 見るため稼ぎ 溜めしとか
その昔、京都ではどんなに景気が悪くても、どんなに切り詰めた生活をしていても、年の瀬を告げる顔見世には着飾って出かけたといいます。それほど、歌舞伎は京の庶民に愛された風俗。その人気の興隆を支えた浮世絵を、往時の技で蘇らせている浮世絵師が東山にいます。
その名は立原位貫さん。江戸の職人たちが分業で生み出してきた浮世絵の全ての行程をたったひとりで、しかも江戸の最高レベルで復元する版画家です。
「浮世絵が、版画であることも知らなかったんですよ。ただ、歌川国芳の浮世絵を見てやってみようと、無茶なことを思ったことがきっかけ。でも始めてみれば、どんどん発見があり、楽しくて。一番の驚きは、絵の具。全く自然のものから抽出された色合いなんです。明治からは、化学染料が混じりましたから。紙も同様で、自然の繊維で漉かれたものだけが、自然の絵の具そのものの美しい発色を引きだすことができるんです。」
立原さんは独力で、絵・彫り・摺りの技術を磨き上げ、さらに独学で絵の具を作り出すため、「本物の作品を目にし、色の退色具合から使用された絵の具の素材を突き止めてきた」といいます。
「江戸時代は、無駄のない自然のサイクルの中で循環していました。絵の具も、紙も、版木も、彫刻刀も、すべてがそう。その中から生まれる浮世絵は違和感がない。江戸時代の浮世絵の魅力は、自然のサイクルの中にあるものだけが作り出せるものです。」
創作版画も高い評価を受けている立原さん。彼の江戸時代への思いとこだわりが、この言葉の中に深く静かに、漂っていました。 |
|
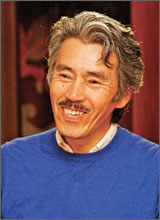
2009年、富山で大量に国芳の版木が発見され見に行ったんです。するとある版木の端に、摺師に指示する言葉が書かれていました。「血の色宜しく」。国芳の作品に対する思い入れを感じましたね。 |