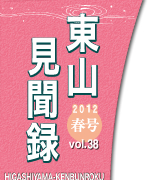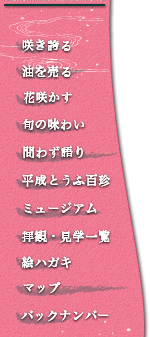ときは、天保六年。幕末の風雲児 坂本龍馬が生を受けた年、京の油小路町に暖簾をかけた店があります。西本願寺にほど近い、油小路通り七条をひと筋下がったところ。菜種油の製造を始め、現在も小売を営んでいる西川油店です。
「京都の油屋はもう二軒のみになってしまいましたが、油小路通りで今も油が買えるって面白いでっしゃろ。この通りはその昔、大阪や伏見、鳥羽吉祥院から多くの人が出入りする産業道路。私がこどもの頃まで米や野菜を積んだ大八車が行き来してたもんですわ」と六代目の西川千大さん。
「“油を絞る”という慣用句が物語るように、菜種油作りは重労働だったんですよ。実を粉にし、蒸し上げ、油を抽出する絞木(しめぎ)に楔(くさび)を打ち込んで油を絞り、漉す。その作業の過酷さは、『油職人は一日に一升の飯を喰らう』と表現されたほど。採れる油は、菜種の重量の二割くらいで、それはそれは大変な仕事だったようです。」
店内を見渡せば、油を実際に精製していた頃の油が染み使い込まれた道具類がずらり。中には、江戸時代の道具も。
「ほら、油でコテコテになってるでしょ。それは、実際に職人たちが長年使い込んだものだから。日本でこれだけのものが残っているところは、そうありません。」
創業以来、京の寺院のお灯明に使われている西川油店の菜種油。今ではその名は轟き、全国の仏さまの御尊顔を照らしています。 |
|
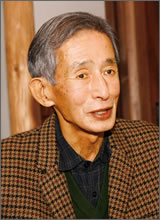
「電気やガスがなかった頃、菜種油は灯明用として高価品でした。一般では匂いと煙が強い鰯油を使っていたようです」とのこと。
|