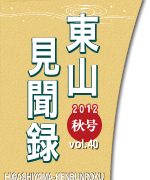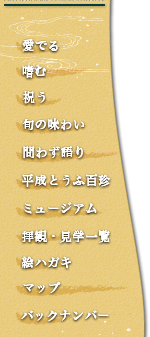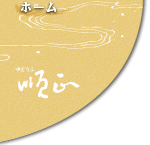萩の宮とも言われる梨木神社。毎年9月の第3または第4日曜日前後には、「萩まつり」が行われ、萩の花を愛でる多くの参拝者でにぎわいます。
萩の花尾花葛花(おばなくずはな)なでしこの花
女郎花(をみなえし)また藤袴あさがほの花
万葉集に山上憶良(やまのうえのおくら)によって読まれた歌です。あさがほ、とは桔梗のことで、この歌に詠まれた七種の花が由来となり、秋の七草と呼ばれるようになったといいます。粥で邪気を払う春の七草とは違い、秋は眺めるためだけの七草。万葉集にいくつも秋の草花が詠まれたのは、古来よりすでに“秋は自然を愛でる”季節という文化が根付いていたことがうかがえます。
この歌の冒頭を飾る「萩」は、くさ冠に秋と書くほどに、季節を代表する花。京でその可憐な萩の花を楽しむなら、真っ先にその名が上がるのが「梨木神社」です。
京都御苑から清和院御門を出たところ。寺町通りに添って鳥居を構える梨木神社は、長月がはじまる頃、参道から社殿前まで、両端の萩が申し合わせたように可憐に花を付け首部(こうべ)を垂れはじめます。
「この神社は、三條実萬(さねつむ)公と、その子実美(さねとみ)公をお祀りしています。その三條家があった地名梨木町にちなんで社名がつけられたようです」と教えてくださったのは、多田宮司。「平安時代から、このあたりは公家のお屋敷が立ち並んでいたようで、その頃から、秋の訪れを告げるように萩が咲き誇っていたのでしょうね」。
いと色深う
枝たおやかに咲きたるが
朝露にぬれてなよなよと
ひろごり伏したる
枕草子 清少納言
秋風に吹かれ、しなやかに振れる萩の繊細な風情が、かの清少納言にはか弱げに映ったようですが、元来萩はさにあらず。たとえ冬に根元まで刈り取られても、春になると若葉を驚くほど力強く八方に広げる様から、「生(は)え木」と呼ばれ、「はぎ」となったとか。
可憐ながら逞しい、数百株もの萩の花が境内を彩る頃、あちらこちらに短歌が添えられ、多くの人のこころを楽しませてくれます。
【上】醒ヶ井(さめがい)、県井(あがたい)とともに、京の三名水に数えられる「染井の井戸」があります。その水は、甘くまろやかな味で茶の湯にも適しています。
梨木神社
京都市上京区寺町通広小路上ル
TEL:075(211)0885
|