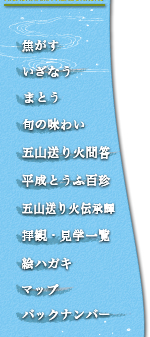「匂ふ」「薫る」「くゆる」などの表現が『源氏物語』に多く記されているように、平安の時代から薫物(たきもの)が公家のたしなみとされてきた京。すっと立ち去った後に、存在をあらためてほのかに漂わせることで、異性の心を惹きつけたとか。吉田兼好は『徒然草』で、そんな香りの教養を「追風用意(おいかぜようい)」と表しました。
遠い昔より匂いの文化も牽引してきた京では、お天道さまの日差しが盆地の湿度を上げる夏、雅やかな香りが頂点をむかえます。創業安政二年、日本で唯一のにほひ袋専門店『石黒香舗』の五代目女将石黒洋子さんは、こう語ります。
「にほひ袋は、四季によって香り方が違うんです。冬などの比較的乾いた時期は、香りがどことなく薄く感じますし、湿度の最も高くなる祇園祭あたりは、強く香りが立ちます。面白いことに春の葵祭の頃から、まるで祇園祭を目指すかのように匂いがどんどん強まっていくんですよ」。
店内で一つひとつ手作業により、金襴や友禅など、鮮やかな袋に詰められるのは十種の香木です。石黒香舗さんの暖簾をくぐると薫ってくる特有の穏やかで重みのある香りは、天然ものだけを使用している証。白檀(びゃくだん)・丁字(ちょうじ)・桂皮(けいひ)・茴香(ういきょう)などから、永年独自に吟味、調合され到達したものです。周囲に振りまくのではなく、匂いの方へ引き寄せる不思議な引力のような香り。心にも平穏をもたらしてくれます。
和装の帯締めに下げるのはもちろんのこと、汗ばむ季節にジャケットの内ポケットに忍ばせれば、平成の追風用意。颯爽とまとった匂いは、夏の湿り気を帯びた空気に乗って、柔らかで奥ゆかしい残り香を漂わせることでしょう。 |
|

「匂いと虫除けの持続期間は巾着大で一年間が目安。詰め替えも承っていますので、永年にわたって足をお運びいただいているお客さまも。新たな試みとして、スマートフォン袋の販売も始めましたよ。」  |