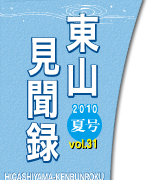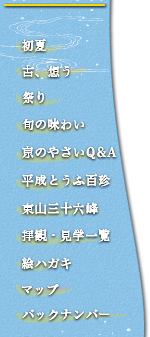|

京の街から眺めれば、北にそびえ立つ鞍馬山。冬なら、街中は晴れていても、そこは純白の雪景。古来、京にとっては異界への入り口とも、北の鎮護(まもり)ともされ、現代では、信じられないほど豊かな自然が息づいている聖地です。
牛若丸と名乗ったころの義経が駆け回り、天狗さんに兵法を学んだという木の根道を登るか。それともパノラマ電車〜ケーブルで自然をゆったり満喫する旅を楽しむか。いずれにしても、山頂の鞍馬寺本殿にたどり着くと、そこは夏でも涼しい風が吹く別世界。さまざまな鳥の声が聞こえ、チャンスに恵まれれば、ヤマネやテン、美しいルリボシカミキリにも出会えます。宇宙の森羅万象を司る尊天(そんてん)がましますという、聖地の“霊気”が、目には見えなくても満身に感じられてきます。
先祖代々この山に暮らし、山の仕事で生きてきた人々が繰り広げる勇壮な行事。それが毎年6月20日午後2時から行われる「竹伐り会式(たけきりえしき)」です。その源は遠く9世紀に始まるといいます。
「当山の中興の祖、峯延(ぶえん)上人が修行中に大蛇に襲われたのを法力で打ち破られました。竹伐りで切られる竹は、退治された雄の大蛇を表わしています。もう一匹、雌の大蛇もいたのですが、この雌は鞍馬山の水を絶やさないことを誓ったので命を助けられ、閼伽井護法善神(あかいごほうぜんしん)様として今も祀られています」。そう語ってくださったのは、鞍馬山博物館の学芸員、曽根祥子(そねしょうこ)さんです。
この竹伐り会式には、災いを断ち切り吉事を招く破邪顕正(はじゃけんしょう)と、水への感謝、五穀豊穣の祈りが込められているとのこと。行事にたずさわる里人は鞍馬七仲間のうち、大惣仲間(おおぞうなかま)、僧達(そうだち)仲間、宿直(しゅくじき)仲間で、仲間によって役割が決っており、山刀で竹を伐るのは大惣法師仲間と呼ばれます。室町時代そのままの世界を連想させますが、現代社会の波は確実に山里に押し寄せていて、普段はサラリーマンとして働く人も多いとか…。
「竹を伐る山刀は正真正銘の真剣です。間違いがあっては大変ですから、竹を伐る仲間はおよそ一週間、精進潔斎をします。別火(べっか)といって、家族とは別の火で煮炊きをして身を清めながら、行事に使うわらじを編み、刀を研ぎます」。
長さ4メートル、太さ10センチの青竹を伐る竹伐り会式。丹波座、近江座に分かれ、早く竹を伐った側が今年の豊作を約されるというようになったのは、江戸時代以降のことだそうです。
|
|

鞍馬寺の尊天は、毘沙門天、千手観音菩薩、護法魔王尊の三身一体。境内やお守りに虎の姿があるのは、毘沙門天のお使いであることから。
「毘沙門天のお使いは虎だけでなく、ムカデもなんですよ。しょっちゅうお目にかかっています(笑)」。自然豊かな鞍馬。星が大きく見える夜も美しい。 |