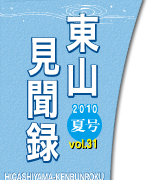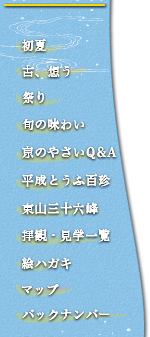|

京都を旅行したおみやげに「和菓子」を…。という旅人は数多いでしょう。羊羹、まんじゅう、だんご、和菓子と聞いて思いだすのは、室町時代からの茶道文化のなかで作り出され、洗練されてきたお菓子です。では、茶道以前の日本人は、どんなお菓子を食べていたか?
時代をウンとさかのぼった奈良時代、大和の国には、現代の私たちの想像を超えたお菓子がありました。和菓子ではなく「唐菓子(からくだもの)」と呼ばれるもので、千三百年の長い長い歳月を経た現代、当時の姿そのままの唐菓子が手に入るのは、京都・祇園石段下にある亀屋清永さんただ一軒。
「遣唐使がもたらした唐菓子にはいろいろな種類があったようですが、団喜と呼ばれるお菓子のうちの清浄歓喜団を作り続けてきました。京都では“お団”として親しまれているお菓子です」と語るのは、十七代目の当主・前川清昭さんです。
お店の奥からは、現代の生活ではあまりなじみのない芳香が漂ってきます。
「白檀(びゃくだい)、桂皮(けいひ)、竜脳(りゅうのう)など七種類のお香を一子相伝の調合で練り込んでいるんですよ」。いずれも、仏教において荘厳な場を創り上げるために使われた「清め」のお香を使い、それを胡麻(ごま)油で揚げる。素材、製法ともに、和菓子のイメージからはかけ離れています。茶道で用いられることは極めてまれなようで、主に用いられるのは仏事。なにしろ、京都は御所があり、各宗派の大本山がそこここに点在する土地柄です。奈良では滅んだ唐菓子も、京都では脈々と受け継がれてきました。
「天台宗や真言宗などで仏前のお供えに用いられています。製法も、天台宗の総本山である比叡山延暦寺の阿闍梨(あじゃり)さんから秘法を伝えられたといいます。作るときには前日の夜から精進潔斎をして、匂いが移ってはいけないのでネギ、柑橘系も口にしません。全国のお寺さんから御注文をいただくので、月の半分は精進潔斎していることになります」。
前川さんが語る座敷の床の間には、昔、御所やお寺に清浄歓喜団を納めるときに用いられた「行器(ほかい)」という器が置いてありました。美しい螺鈿細工が施されています。その風格ある姿からも、往時のお菓子がいかに貴重なものであったかが伝わってきます。
|
|

清浄歓喜団を一口食べると、ぷわぁ〜と香の香り、胡麻油の匂いとともに、小豆あんが口のなかに広がります。「小豆あんを用いるようになったのは江戸時代の中期以降と伝えられています。奈良時代には、栗、柿、アンズなどの木の実に、かんぞうや甘葛(あまづら)で味を付けて餡にしていたようですね」。 清浄歓喜団の袋のなかには、日本のお菓子の歴史がギュッと詰まっています。
|