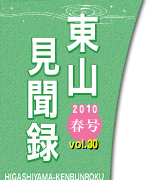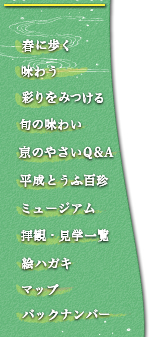|

ぽかぽか陽気の続く春は、昔も今も旅行の季節。平安王朝の頃にも、紀州・熊野詣が貴族たちの間に流行し、都から往復に幾日もかけて遙々と旅をしていったといいます。とりわけ、後白河上皇は生涯に三十数回も熊野詣をされたといいます。
交通事情の良くない当時、長い道中には疫病、山崩れ、夜盗、さまざまな災厄がありました。道中ばかりではなく都の内で移動するにも、災厄を逃れるために他人の屋敷へ寄って「方違(かたたがえ)」「方除(ほうよけ)」をしたという話があります。灯りが乏しかった時代、夜の闇さえも魑魅魍魎(ちみもうりょう)の跋扈(ばっこ)する世界に思えたのでしょう。陰陽道の知恵により、悪い方角へ足を踏み入れないようにと考え出されたのが方除です。
「平安京を護るため、都の入口に当たる南の地にお祀りされたのが、ここ城南宮です。後世の江戸時代には御所の裏鬼門に位置する方除の大社として信仰されました。」と教えてくださったのが、宮司の鳥羽重宏さん。城南宮の歴史ははるか神功(じんぐう)皇后の時代にさかのぼるといわれ、また、平安時代後期の白河上皇から鎌倉時代初めの後鳥羽上皇に至る百数十年の間は、この地に、上皇の別荘である「鳥羽離宮」が築かれていました。
「白河上皇、鳥羽上皇は、熊野詣の道中の無事を祈るために精進潔斎され、鳥羽離宮から出立されました。そののちも悪い方角を除け、旅や引っ越しの安全を祈る人々で賑わっています」。
4月、神苑のそこここに咲く桜の花びらが風に舞い、遣水の水面を薄紅に染めるころ、神のご加護に感謝して方除大祭が催されます(今年は4月9日〜11日)。また、王朝の風雅をしのぶ「曲水の宴」は4月29日。こちらは、平安装束の男女が歌を詠み杯を傾けた古式に則った行事です。『源氏物語』に記された植物が植えられた庭園も広がり、行事に、景色に、平安の人々の想いが伝わってきます。
|
|

「昔から、家の気になる方角や場所にまく“清めの御砂”をお授けしてきました。ところが、現代ではマンションなど土の所が無い家も多くなっています。そういうご家庭では、小振りの錦の袋に入った清めの御砂を、部屋に置いておかれるといいですよ」
|