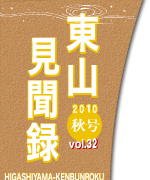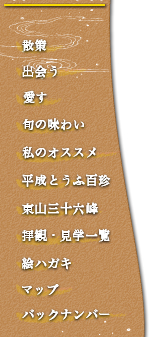|

京都を歩く楽しみは、千二百余年の歳月にわたって人々がまるで織物を織り上げるように、無数の歴史を重ねてきた景色を味わえることです。たとえ道はすっかり舗装されていても、寺院の塔や古い商家が道脇にたたずまいを残し、ときおり出会う地名にも、さまざまな物語が感じられます。
修学院から比叡山へと向かう途中にある「きらら坂」もその一つ。正しくは「雲母坂」と書きます。雲母(うんも)というのは鉱物の一種で、きらきらと輝くのが特徴です。きらら坂の土のなかには、この雲母が多く含まれていたところから、地名になったと言い伝えられています。
では、昔、雲母の採掘場でもあったんかと…というと、そやないんです。ここは京の都から比叡山への街道。比叡山は日本仏教の母山といわれ、平安王朝のころから深く信仰された延暦寺があるお山です。
街道にはさまざまな人が往来しました。千日回峰行、比叡山だけでなく京の町々までも回って修行する行者さんたちも、この道を通って行きました。都から延暦寺へ向かう公家や武士なども通って行きました。
「この家は、京の街と比叡山を結ぶ街道に設けられた番所だったんですよ」
そう語るのは田邉佳一(たなべ よしかず)さん。江戸時代中期の元禄年間から代々、きらら坂に住んできた田邉家の当主です。その旧家は独特の構えで、高貴な公家を迎えるための式台玄関、番所として往来の人々を監視するために用いられた小窓、そして山道を歩く人たちが休むための、茶店としての空間。いろいろな階層の人たちが街道をゆき、いずれの人々とも、この旧家が関わっていたことを物語っています。
この屋敷の前を通り過ぎたら、比叡山まで二時間、休む場所もなく歩くことになります。
「そんな道中の人々に出したのが、きらら漬です」
田邉さんの家族が今も作り続けている、小ナスを白味噌に漬けたものです。砂糖などの甘味がめったに手に入らなかった時代、甘い白味噌はお茶うけに最適でした。また、汗を流して坂道を登る人には、塩分を補給するのにも適していました。街道をゆく人々と関わりの深い旧家ならではの、もてなしの味です。
秋の東山を歩く散策。街道脇の旧家で一休みして、ふたたび京の街中へと戻るか。それとも昔さながらに比叡山を目指すか。ゆっくり時を忘れて思案するのも、この季節ならではの楽しみです。 |
|

伝えられてきた「きらら漬」は、田邉さんの家族を中心に数人で作り続けられています。大都市や京都の市街地に出店を出すこともなく…。そこでしか出会えない味わい。これもまた散策の楽しみの一つです。 |