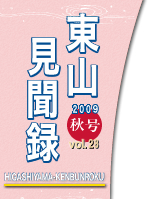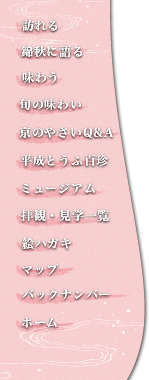|

京都を旅していると、不思議な地名としばしば出逢います。たとえば、地下鉄の駅にもある「鞍馬口」という地名。鞍馬山の登り口にしては、山からあまりにも離れ過ぎています。実は、下鴨から深泥池を経て鞍馬へと到る鞍馬街道の入り口…という意味があります。京が都であった時代、都に入る入り口=七口の一つでした。明治中期までは鞍馬口村という農村もあり、京の街へ大根や茄子を出荷していたといいます。
畑のなかを街道が通る、のどかな景色にあった一軒の茶店。そこで売られていたのが名物の「御鎌餅」です。いつしか茶店は消えたものの、農具の鎌をかたどった名物の美味さは人々の記憶に残り、明治も三十年ごろになって、一人の宮大工さんがその餅を復活させます。−なんとも、ほのぼのとした昔ばなしですが、百年あまりもたった今も、御鎌餅は作りつづけられています。
「稲を刈る鎌に見立ててあるのは、豊作を祈り、福を刈り込むという願いが込められているんですよ」と語るのは、大黒屋鎌餅本舗のご主人・山田充哉さんです。昔なじみのご近所さん、評判を聞いてふらりと立ち寄った旅行者のお客さんの応対をするご主人。その奥では、お母さんがせっせと御鎌餅をならしては、杉の皮のへぎにくるむ。「二人きりで作ってますので、前もって注文をいただかんと、ようけはできません」。じっくりと炊き上げた餡をくるんだ御鎌餅のように、ご主人の物腰はなんともやわらかです。
木造のこのお店があるのは、寺町通今出川4丁目の界隈。昔どおり、静寂な寺院と住宅が並ぶ一角です。静けさのなかで、一つ、また一つと、今ではすっかり貴重になった杉皮で御鎌餅をくるむ風景。ここには、江戸時代の、そして明治の、茶店や秋の農村の情景が、ほのかな木の香とともに残っています。
|
|

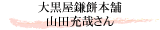
お店のなかには、修学旅行生から贈られた寄せ書きが…。「体験学習で、御鎌餅を二つか三つずつ造ってもらい、お土産にしてもらってます」とのこと。昔ながらのお菓子、この秋の旅のお土産の一つに。すぐ近くには、織田信長や森蘭丸の墓所「阿弥陀寺」があります。
|