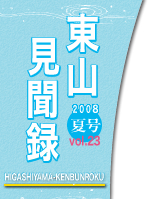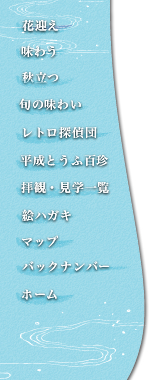暦では立秋を迎えても、盆地の京都にはまだまだ炎暑の日が続きます。そんな京都でも毎夏、もっとも“熱い!”思いをしているのは、五山の送り火を燃やす人たちでしょう。8月16日の宵、京の夜空を焦がす大文字、左大文字、妙法、船形、鳥居形の火。何十基もの火床を燃え上がらせる現場を想像すると、「いったい、どんな人たちが燃やしているんだろう?」と疑問もわいてくるところ。五山のなかでも、とりわけ広く親しまれている「大文字」に携わる、保存会の理事長・藤田征平さんにお話をうかがいました。
「全国からお越しの方にとっては観光なのだと思いますが、私たちにとっては、お盆にお迎えした先祖の精霊を送る信仰の行事なのです。いつのころからか、『大文字焼き』と呼ばれるようにもなりましたが、あれは間違いなんです。先祖を送るための『送り火』なんです。大文字の火を守り続けているのは、52軒の家からなる保存会です。今では住まいも多少は離れていますが、かつては、どの家も銀閣寺さんの門前にあった家ばかりです」。
銀閣寺といえば、茶道・華道・能楽など東山文化の起源に深い関わりを持つ足利義政の山荘・東山殿の跡。五山の送り火の起源については諸説ありますが、この室町八代将軍・義政公が始めたともいわれています。およそ500年の昔です。長い歳月の間には、数々の秘話もありました。
「いつの時代かはわかりませんが、昔は、市原野に『い』の字、観音寺村に『長刀』、北嵯峨には『蛇』など、今は絶えてしまった送り火があったと言い伝えられています。また、戦時中には『白い大文字』というのもありました。灯火管制の厳しかった時代のこと、夜ではなくて朝に、地元の小学生たちが白いシャツを着て山に登り、ずらっと並んで大の字を作りました。ウチの兄もその一人でした」。
さまざまな時代の波を乗り越えて、今に受け継がれている五山の送り火。先祖を送るこの行事が終わると、あいかわらず続く暑い日々のなかにも、どこか秋の気配が感じられるようになります。この壮大な火は、長かった夏を送る火でもあるのです。
その風情を楽しめる特等席は鴨川の堤です。
大文字を待ちつつ歩く加茂堤
高浜虚子 |
|

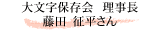
伝統を守るための働きは、たった一晩に限ったことではなく、その準備に長い期間を要します。「送り火の火床に使う赤松は、樹齢80年ほどのものを春に切り出し、割り木にし、およそ半年ほど乾燥させないとよく燃えてくれません。さらに、その火床の松割木の周りを麦わらで囲むのですが、近年は麦わらの入手が難しくなっています」。
|