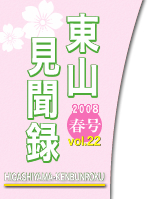|
日本全国どこの街でも、町内に一つはお祭りやおみこしがあって、子どもたちはワイワイ楽しんでいるけれど、その世話役に当たった時の面倒なこと……。思わず「うん、うん」とうなずいている方も多いでしょうが、京都にはスケールがケタはずれに違う“世話役さん”たちがいます。
北区紫野界隈の農家や元農家11軒が、2年ずつの持ち回りで世話役を務めているのは、京都三大奇祭の一つ「やすらい花」。国の重要無形民俗文化財に指定されている上に、その歴史たるや、千数百年前の平安時代にさかのぼるという古さです。現在、「今宮やすらい会」の世話役である会長を務めているのは北川敏彦さんです。その胸中をうかがうと、「祭りの楽しみというのは、あんまりありませんなぁ。お神酒を呑んでおみこしを担ぐような、パァ〜ッと発散するお祭りやないから…」。ところが、お祭りのことを語っている北川さんの言葉には熱意がこもり、その表情も楽しそうなのです。
「やすらい花というお祭りは、紫野に2つ、上賀茂、西賀茂にそれぞれ1つずつ、合計4つ伝わっています。よく見てもらうと気が付くんですが、装束や節がちょっとずつ違うんですよ。足袋をはいていたり、はいてなかったり…。
このお祭りは、昔、花が咲くころになると流行った疫病を退散させるために、風流傘に疫病を閉じ込めて、神前に納めます。この時に、赤や黒のシャグマという長い毛を振るわせながら、“鬼”が舞いを奉納するんです」。
家々の疫病神を払うため、先頭を行く頂(てっぺい)、旗を掲げる大旗、平安時代さながら装束をした白丁、現代では歌舞伎舞踊の『娘道成寺』ぐらいでしか見ることのなくなった鞨鼓(かっこ)を持った子鬼、太鼓を打ち鳴らす大鬼など、総勢50人ほどの一行が約100戸を回ります。
「年に一度、お祭りの日に使う装束や道具ですが、年中いろんな工面をせなあきません。子鬼が打つ鞨鼓がありますが、子どものことやから面白がって叩いてるうちに、じきに塗りが取れてしもたりね」。広〜い意味ではパーカッション(打楽器)の仲間とはいえ、街の楽器屋さんに売ってるんでしょうか?「京都に職人さんが居るんですよ。たいがいのものが京都で入手できます」とのこと。千年前の祭りが伝わっている京都、装束や道具の技が伝わっているのも京都ならではです。
午前11時に地元の光念寺に参集し、途中、所望される家の前で踊りを踊ったり、疫病除けに傘に入りたいという頼みに応じながら、足半(あしなか)というワラジを履きつぶし、子鬼の子どもたちがげ〜んなりするころ、午後3時、いよいよクライマックスの踊りの奉納。
「踊る人、囃す人、一糸乱れない姿が……やすらい花の魅力ですなぁ」。
|
|

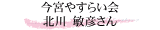
なにしろ、国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭。時には全国のお祭りといっしょに公演されることも。「その遠征がまた大変なんですよ」。伝統を守る世話役さんたちの苦労は尽きません。 |