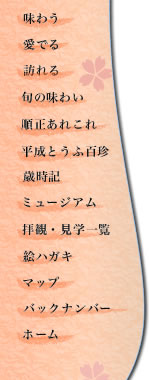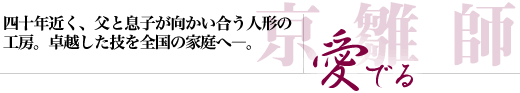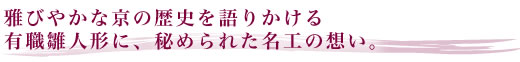繁華な大通りから一筋外れ、昔ながらの家々が並ぶ一角に「桂甫作 安藤人形店」はあります。仲良く顔を合わせて座るのは男雛・女雛…ではなくて、そのお雛様に綺麗な装束を重ねていく二代目・安藤桂甫さんと息子の忠彦さん。
父と子が互いに向き合って仕事をするようになって四十年近くも経つそうですが、「私は父から技を教えられたことはなく、息子にも技を教えたことはありません。習うよりも見て覚えていくものなんですよ。積み重ねが大切ですね」。優しい笑みをたたえながら、技を身に付ける厳しさを語る桂甫さん。とりわけ難しいのはお雛様に着付ける十二単の襟です。彩りも模様も美しく、西陣織りの裂(きれ)が襟に重ねられる。それが、名を書き入れて全国へ送り出される「卓越技能者現代の名工 桂甫作」のお雛様の特長です。
「お雛様を作っていますとね、心に語りかけてくれるんですよ。そして私も『どこのご家庭で飾ってもらえるんやろね? どんな場所やろ? どんな場所でもその場を引き立ててね』と心の中で語りかけるんです。ご家庭で一年に一度箱の中から取り出されて飾られると、きっとお雛様は喜んでいると思います。そういうお雛様と思わぬところで”再会“できたら、ご縁を感じてホッとしますね。そんな時が、京雛師の仕事をしていて一番うれしいんですよ」。
祖母から母、母から娘へと一組のお雛様を大事に伝えていく家庭もあります。「でも、昔から言われているのは一代一組です。生まれた娘さんの病気や災いを代わりに引き受けてくれるのがお雛様なのですから。娘さんがお嫁入りされる時に持って行かれるのではなく、親御さんがお雛様を飾られて、娘さんの幸せを想われるものとされています」。
金糸を一本も使わずに品格を重んじるのが有職雛人形。そんな”小さな京都“に心を込める父子の姿が老舗の工房には生きています。 |
|

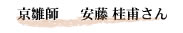
“京”の美を作り続ける桂甫さんは、池坊文化学院の教授であり、かつては南座の「素人顔見世」の名優!まさに京の伝統に生きる風流人です。

 |